着物のたたみ方(本だたみ)ー田中志津子 着付教室 Vol. 3 скачать в хорошем качестве
Повторяем попытку...
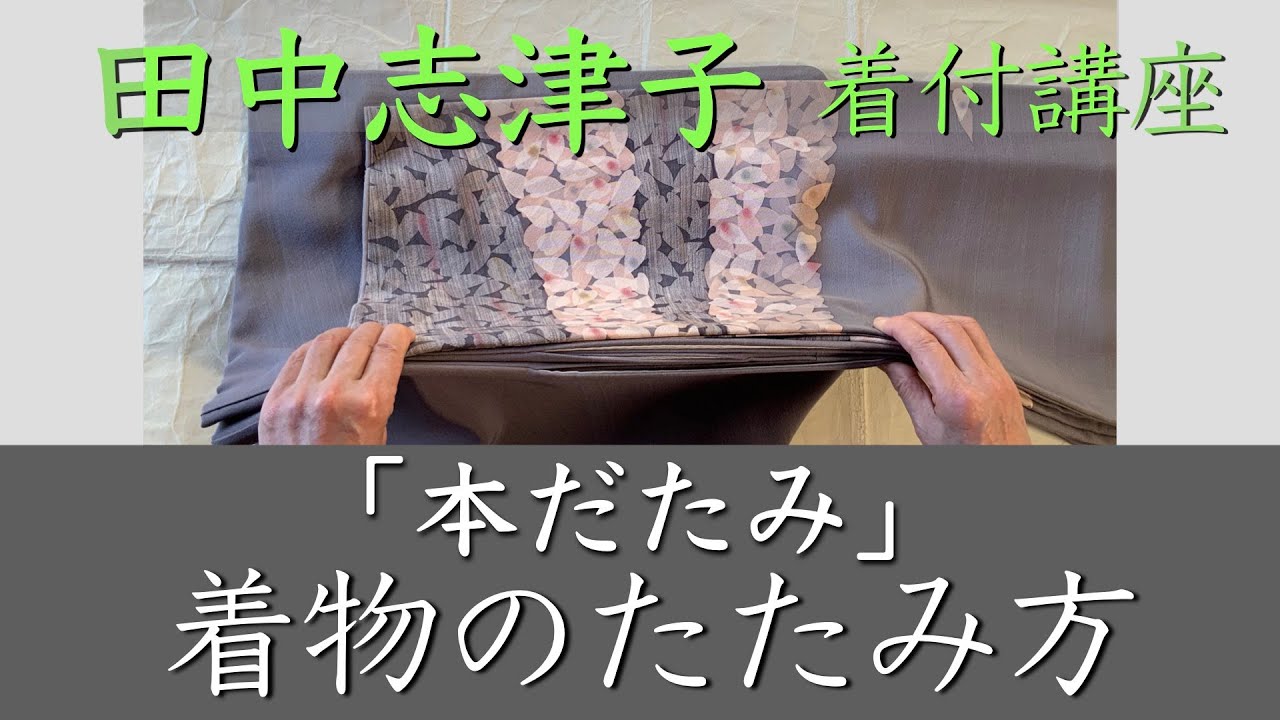
Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: 着物のたたみ方(本だたみ)ー田中志津子 着付教室 Vol. 3 в качестве 4k
У нас вы можете посмотреть бесплатно 着物のたたみ方(本だたみ)ー田中志津子 着付教室 Vol. 3 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
-
Информация по загрузке:
Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон 着物のたたみ方(本だたみ)ー田中志津子 着付教室 Vol. 3 в формате MP3:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
着物のたたみ方(本だたみ)ー田中志津子 着付教室 Vol. 3
基本的な「本だたみ」をご紹介致します 着物全体を広げて畳んでも良いですが 今回はあまりスペースを取らずに 衣紋側と裾側に分けて畳む方法です 仕立て上がり時の折り目に沿って 新たな折り線を増やさないように 丁寧に畳みましょう! 大切な着物を畳む時間は 晴れた日にお雛様をしまう様な 至極のひとときにもなります 色柄の由来や生地の種類を確かめたり 染めや刺繍の素晴らしさを愛でたり 着物を誂えた時、お譲り頂いた方の事を 思い出したりします 次に着る時の帯や小物の取り合わせを考えたり もちろんシミや汚れ、 ほころびがないか確認しながら畳みます ●この動画の着物は「花びら」 スタジオウフ 園部月美のオリジナル 色留袖風訪問着です 「色留袖」は帯の上になる部分には 柄はありません この着物はよく見るとうっすらと 春風のように斜めに刷毛目が入ってます 上前から裾には たくさんの花びらが重なり合ってます。 格付けでいうと「訪問着」になりますが 「色留袖」の様なキリッとした雰囲気もあります 変わり縮緬の白生地に溶かした 蝋(ロウ)で花びら一枚一枚 描いては染め〜描いては染め〜描いては染めを 繰り返して花びらを敷きつめながら 紅色の「指し色」をして 白→薄桜→薄墨→グレー紫と 染め重ねております。 「八掛け」(裾回し)には 数枚の花びらが描かれてます 「八掛け」の柄はほとんど見えませんが 着物の隠れたお洒落の一つです 「染め月」 制作動画は↓ • 染め月 ★着物、長襦袢、羽織、道行コートなどを 畳む時にはまず衿紋(衿、肩、袖側)が左、 裾が右になるように広げて置きます 日本文化では左が格上と 覚えておくと良いと思います ❶衣紋(首後ろの衿部分)を 左に置いて広げます ❷裾側半分からたたみ始めます 手前(下前の脇縫い)の脇線を最初にたたみます ❸下前の衽(おくみ)を手前に返します 八掛(裾の裏地)が上になります ❹上前の衽(おくみ)を上に重ねます( 手を合わせて拝むような形) 左右の衽が一番内側で重ります ❺向こう側(上前の脇縫い) 脇線を手前(下前の脇縫い)の脇線に重ねます 背縫い部分もまっすぐにたたまれてるか確認します ❻そうしましたら裾半分を右側にずらして残りの衣紋側(上半分)をたたみます ❼背縫い部分(紋の位置の上)に三角の折り目がありますので折り目通りに凹ませるようにたたみます ❽左手で衿肩あきの交差点を 右手で左右のの衿先を重ねて持って まっすぐになるよう引っぱります この部分は丁寧にたたんでください ❾身頃も重ねます 左袖を袖付けから身頃に折り返します (右袖はそのまま) ❿右手首まで使って衿先部分を押さえ 左手で裾部分をしっかり持って 二つ折りにします ⓫脇縫いと袖付けの重なりを しっかり持って右袖を下に折り入れます 掌で「手アイロン」しながら 変な重なりやシワがないか 確認してみて下さい 触って怪しいところはたたみなおして下さい 経糸と緯糸をしっかり整えてたたみ 段差のないように保管しましょう! 絹の着物は清浄作用があるのか? 不思議ですが次にお召しになる時に はキリッと綺麗になってますよ! ★[たとう紙] 着物用、帯用、長襦袢用などサイズが色々あります 永久ものではありませんので 2〜3年に一度はシミ汚れがないか点検して下さい ★[着物枕] 着物や帯の保管用に綿を入れて作られている 棒状のものです 折り目部分に挟んでおくとシワを防げます ★ [うす紙] 刺繍、箔、胡粉などが施してある部分に 挟んで使います 段差部分に折りたたんで使う事も出来ます こちらもご覧ください スタジオウフ https://www.studio-oeuf.com/ 園部月美 染め月 https://www.sometsuki.com/