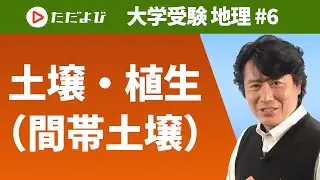【高校地理】3-12. 植生と土壌 | 3. 世界の気候 скачать в хорошем качестве
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: 【高校地理】3-12. 植生と土壌 | 3. 世界の気候 в качестве 4k
У нас вы можете посмотреть бесплатно 【高校地理】3-12. 植生と土壌 | 3. 世界の気候 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
-
Информация по загрузке:
Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон 【高校地理】3-12. 植生と土壌 | 3. 世界の気候 в формате MP3:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
【高校地理】3-12. 植生と土壌 | 3. 世界の気候
はい、皆さんこんにちは。高校地理の授業動画、「世界の気候」第12回は「植生と土壌」です。 【目次】 0:00 イントロダクション 0:38 気候と植生の関係 2:12 各気候区の植生 4:57 気候と土壌の関係 6:32 各気候区の土壌 9:00 成帯土壌と間帯土壌 【確認問題のURL】 https://forms.gle/DCXbsTfCMmLLYHyf8 【今回の動画の内容を文章と画像で確認されたい方はこちら】 https://www.geography-lesson.com/vege... 【動画の目次はこちらのホームページから】 https://www.geography-lesson.com/ #地理b #植生 #土壌 #気候 #ケッペン #気候区分 #高校地理 #ラトソル #ポドゾル #テラローシャ #テラロッサ #サバナ # 「植生と土壌の特徴が覚えられない!」 ということですが、この分野って高校生の皆さん、苦手意識を持っている人も多くて丸暗記になりがちなんですね。 「ラトソル、赤!ポドゾル、、、何だっけ?」みたいになりがちなのですが、どうしてそうなるのか、原理原則から解説したいと思います。 ではいきましょう。 動画は大きく3つのパート、 1 気候と植生 2 気候と土壌 3 成帯土壌と間帯土壌 という構成になっています。 なお、この動画では、全体像を意識していきますので、一つ一つの植生や土壌の詳しい説明は、前回までのA気候からE気候までの動画も、合わせてご覧ください。 1.気候と植生 まずは、気候と植生との関係です。 植生というのは、ある地域を覆っている植物の集まりです。 そして、ケッペンの気候区分は、そもそもこの植生をもとに考えられたので、気候と植生には、はっきりしたつながりがあります。 こんなモデルをイメージしてください。 横軸に気温と降水量、縦軸に、その場所の植生の背の高さ、植物の種類、植物の密度をとった図です。 植物は光合成で育ちます。そして、光合成は、気温が高いほど、降水量が多いほどしやすいので、この図でいう右側ほど、植物はぐんぐん育って、そこの植生の高さは高くなるし、植物の種類は多いし、密度も高くなる、という傾向が見られます。 これをイメージしながら、植生を整理しましょう。 この2つの四角は、 縦軸が気温で、横軸が降水量を表しています。 上の方が気温が低くて、下に行くほど気温が高い。 左の方が乾燥していて、右に行くほど降水量が多い。 という見方をします。 つまり、右下ほど、気温が高くて、降水量も多い、ということです。 さっきのモデルと合わせて考えると、右下に近い植生ほど、大きくて、種類は多くて、密度は高くなる傾向があります。 じゃあ一番右下って具体的に何かって言うと、気温が高いので気候は熱帯で、その中でも降水量の多い熱帯雨林気候、Af気候、となります。植生は名前のとおり熱帯雨林。一年中蒸し暑くて植物はどんどん成長して背は高く、色んな植物が鬱蒼と生い茂ります。 その左側に行くと、気温は高いけど、降水量が少し減るというところなので、雨季と乾季が別れる熱帯、サバナ気候、Aw気候で、植生の名前もサバナとなります。乾季には植物同士で水の取り合いになるので、密度はまばらで、背の低い樹木が生える植生となります。 今度は上に行くと、降水はあるけど気温が少し下がる場所なので、温帯、C気候です。植生は、ひっくるめて温帯林と呼ばれます。 温帯林にはいろんなタイプの樹木があって、比較的暖かい場所では、冬でも葉っぱを落とさない常緑広葉樹、寒い場所では、冬に葉っぱを落とす落葉樹や、葉っぱが針みたいにとがった針葉樹が増えていきます。これらが混ざった植生が、混合林あるいは混交林と呼ばれます。 気候区ごとに見てみると、 地中海性気候、Cs気候では、夏の乾燥に耐えられるように、小さくて硬い葉っぱを持った常緑広葉樹となり、硬葉樹林と呼ばれます。代表例はオリーブ、コルクガシなどです。 冬に乾燥する温暖冬季少雨気候、Cw気候では、C気候の中では緯度が低くて暖かい場所に分布するので、葉っぱがテカテカした常緑広葉樹となり、照葉樹林と呼ばれます。代表例はシイ、カシ、クスノキなど、秋にどんぐりが拾えるようなイメージの木です。 西岸海洋性気候、Cfb気候では、緯度が高くて気温が低いので冬には葉っぱを落とす落葉広葉樹となり、特にブナの木が代表です。 最後に温暖湿潤気候、Cfa気候ででは、常緑広葉樹、落葉広葉樹、針葉樹の混ざった混交林あるいは混合林となります。 続いて左側に行くと、降水量が少ない乾燥帯に入って、ステップ気候、BS気候で、植生の名前もステップです。木は生えませんが、短い雨季に草が生えて草原が広がります。 一番左側は、全然雨の降らない砂漠気候、 BW気候で、植物はほとんど生えず、植生もそのまま砂漠、となります。 そして、図の上の方にいくと、気温が低くなって、亜寒帯、D気候になります。冬の寒さに耐えられるごく少数の種類の針葉樹林だけで構成された広大な森林、タイガが広がります。 その上は寒帯、E気候になって、気温は低くて木は生えず、植物の高さも低くなります。 ツンドラ気候、ET気候では、夏には地面の雪や氷が溶けて、そこに地衣類や苔類などが生える、ツンドラという植生になります。 一番上の氷雪気候、EF気候では、1年中雪と氷に覆われた永久氷雪が広がります。 2.気候と土壌 続いては、気候と土壌です。 土壌は、こんなモデルをイメージしてみましょう。 縦軸が土壌の肥沃度、横軸が気温と降水量です。 植生と違って山型の関係になり、気温も降水量も中間くらいの時に、肥沃度は一番高く、栄養たっぷりの土壌になります。 これはなぜか。土壌の肥沃度、つまり土の栄養ってそもそも何かっていうと、地面に落ちた動物や植物の死骸が、微生物で分解されてできた、腐植というものが、どれだけたくさんあるかで決まるんですね。 ホームセンターの園芸コーナーに行くと、腐葉土って言って、落ち葉を発酵させた黒っぽい肥料のようなものが売ってますが、あんな感じのものが、腐植だと思ってください。 気温が低すぎると、微生物の働きが鈍くなって腐植が作られないし、逆に、気温が高すぎると、今度は微生物の働きが活発になりすぎて、腐植が貯まる前に動植物が分解されきって無くなってしまいます。 雨もバランスが大事で、雨が少なすぎて乾燥した場所では、そもそも植物が生えませんし、土砂降りで雨が多すぎると、作られた腐植が流されてしまいます。 そのため、気温と降水量が両方ともほどほどの場所だと、良い土ができるんですね。 さらに、ここに土壌の色も加えることができます。 腐植って黒いものなので、肥沃度の高い土というのは基本的に黒いんですね。 そして、腐植が少なくなって肥沃度が落ちると、黒い色が抜けて、別の明るい色になっていきます。 このモデルを当てはめて考えてみると、 気温と降水量がほどほどの場所ということで、この図の真ん中あたりが、一番肥沃で一番黒い土となり、黒土という土壌がこれにあたります。BS気候からC気候の乾燥した地域にかけて分布し、肥沃度が非常に高い土壌です。 この黒土、主な分布地域では特別な名前がついています。 ウクライナからロシアにかけての黒土はチェルノーゼム、 北アメリカ中央部はプレーリー土、南米ラプラタ川周辺はパンパ土、などです。 特にチェルノーゼムは、世界一肥沃な土壌、土壌の皇帝とも呼ばれます。 第二次世界大戦の際にはドイツ軍がこの土を持って帰ろうとした、なんていうエピソードも残されているほどです。 BS気候でも降水量がもう少し少ない場所だと、植物も少なくなるので、腐植の少なくて色が薄くなった栗色土。砂漠気候では腐植が全然無い砂漠土。そしてA気候では、暑すぎることと雨で栄養分が流されてしまうことから肥沃度の低いラトソルが分布します。ラトソルは赤い色をしているのですが、これは、雨で流されない酸化鉄などが残った色です。 C気候では、温度と降水量のバランスが良いので、黒色土ほどでは無いけど肥沃度は高めの、褐色森林土。 D気候は、寒くて植物の分解が進まないので、肥沃度が低いポドゾルという土壌が分布します。白っぽい色をしているのですが、寒くて水が蒸発しないので、土に色をつけてる物質も全部水に溶けて、下の方に染み込んでいってしまうからです。 ET気候は名前の通りツンドラ土で、これもやはり低温で肥沃度は低いです。雪と氷のEF気候では土壌はありません。 以上、土壌の肥沃度と色を整理してきましたが、ここに土壌のph、酸性かアルカリ性かということも加えておきましょう。 土っていうのは、基本的には酸性だと思っていいです。これは雨の影響で、雨水というのは空気中の二酸化炭素が溶けているためにやや酸性で、その酸性の雨水が含まれるから、土壌も酸性を示す、というわけです。 ただし、乾燥地域、B気候の土壌はアルカリ性です。乾燥地域では地面の水分がどんどん蒸発するので、特に農業のために人工的に水を撒く灌漑をやっていると、地中の水分と一緒に塩類も上の方に吸い上げられて、地表に溜まってしまいます。このため、砂漠土は塩性土壌となり、強いアルカリ性を示します。同じ理屈で、栗色土も弱いアルカリ性を示します。 3.成帯土壌と間帯土壌 最後のパートは、成帯土壌と間帯土壌です。 土壌というのは大きく2種類に分けられます。 一つは、そこの気候や食性の影響を大きく受ける土壌で、成帯土壌と呼ばれます。ここまで見てきた土壌は全てこの成帯土壌にあたります。 もう一つは、母岩といって、土壌のもとになる岩石の影響を強く受けた土壌で、間帯土壌と呼ばれます。 代表的な間帯土壌4つ、レグール、テラロッサ、テラローシャ、レスを紹介します。名前だけでなく、分布地域と、農作物も一緒に整理しましょう。 1つ目はレグール。 インドのデカン高原に分布する肥沃な黒色土で、玄武岩が風化した土壌です。綿花土とも言われ、綿花栽培が盛んです。 2つ目はテラロッサ。 地中海沿岸に分布する赤色の土で、石灰岩が風化した土壌です。地中海沿岸には石灰岩の白い家が多いですが、それとつなげると覚えやすいかと思います。テラが土、ロッサが赤という意味のイタリア語で、直訳すると「赤い土」です。ワインを作るブドウなど、果樹栽培に適した土壌です。 3つ目はテラローシャ。 テラロッサと名前が似ていますが、テラは土、ローシャは紫色という意味で、南米のブラジル高原に分布する赤紫色の土です。レグールと同じく玄武岩が風化した土壌で、コーヒー栽培が盛んです。ブラジル、コーヒー、テラローシャ、セットで覚えておきましょう。 最後4つ目はレス。 風によって運ばれた細かい砂が堆積した黄色い土壌を、ひっくるめてレスと言います。中国の黄土高原にはこの黄色いレスが何十mも積もっていて、春に日本に飛んでくる黄砂は主にここから飛んできています。ヨーロッパ中部にもレスは分布していて、氷河によって削られてできたモレーンの砂が飛んできたものです。特に、ハンガリーのプスタがレスの代表で、小麦の生産が盛んです。 はい、今回の動画は以上となります。 確認問題にチャレンジしたい方はURLはコメント欄からアクセスしてください。 また、感想や質問などあれば、コメント欄にお気軽にお書きください。 それではまた次回!