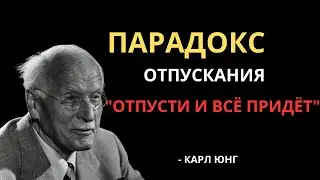жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П —Б–Ї–∞—З–∞—В—М –≤ —Е–Њ—А–Њ—И–µ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ
–Я–Њ–≤—В–Њ—А—П–µ–Љ –њ–Њ–њ—Л—В–Ї—Г...

–°–Ї–∞—З–∞—В—М –≤–Є–і–µ–Њ —Б —О—В—Г–± –њ–Њ —Б—Б—Л–ї–Ї–µ –Є–ї–Є —Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –±–µ–Ј –±–ї–Њ–Ї–Є—А–Њ–≤–Њ–Ї –љ–∞ —Б–∞–є—В–µ: жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П –≤ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ 4k
–£ –љ–∞—Б –≤—Л –Љ–Њ–ґ–µ—В–µ –њ–Њ—Б–Љ–Њ—В—А–µ—В—М –±–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ–Њ жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П –Є–ї–Є —Б–Ї–∞—З–∞—В—М –≤ –Љ–∞–Ї—Б–Є–Љ–∞–ї—М–љ–Њ–Љ –і–Њ—Б—В—Г–њ–љ–Њ–Љ –Ї–∞—З–µ—Б—В–≤–µ, –≤–Є–і–µ–Њ –Ї–Њ—В–Њ—А–Њ–µ –±—Л–ї–Њ –Ј–∞–≥—А—Г–ґ–µ–љ–Њ –љ–∞ —О—В—Г–±. –Ф–ї—П –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–Є –≤—Л–±–µ—А–Є—В–µ –≤–∞—А–Є–∞–љ—В –Є–Ј —Д–Њ—А–Љ—Л –љ–Є–ґ–µ:
-
–Ш–љ—Д–Њ—А–Љ–∞—Ж–Є—П –њ–Њ –Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Ї–µ:
–°–Ї–∞—З–∞—В—М mp3 —Б —О—В—Г–±–∞ –Њ—В–і–µ–ї—М–љ—Л–Љ —Д–∞–є–ї–Њ–Љ. –С–µ—Б–њ–ї–∞—В–љ—Л–є —А–Є–љ–≥—В–Њ–љ жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П –≤ —Д–Њ—А–Љ–∞—В–µ MP3:
–Х—Б–ї–Є –Ї–љ–Њ–њ–Ї–Є —Б–Ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є—П –љ–µ
–Ј–∞–≥—А—Г–Ј–Є–ї–Є—Б—М
–Э–Р–Ц–Ь–Ш–Ґ–Х –Ч–Ф–Х–°–ђ –Є–ї–Є –Њ–±–љ–Њ–≤–Є—В–µ —Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Г
–Х—Б–ї–Є –≤–Њ–Ј–љ–Є–Ї–∞—О—В –њ—А–Њ–±–ї–µ–Љ—Л —Б–Њ —Б–Ї–∞—З–Є–≤–∞–љ–Є–µ–Љ –≤–Є–і–µ–Њ, –њ–Њ–ґ–∞–ї—Г–є—Б—В–∞ –љ–∞–њ–Є—И–Є—В–µ –≤ –њ–Њ–і–і–µ—А–ґ–Ї—Г –њ–Њ –∞–і—А–µ—Б—Г –≤–љ–Є–Ј—Г
—Б—В—А–∞–љ–Є—Ж—Л.
–°–њ–∞—Б–Є–±–Њ –Ј–∞ –Є—Б–њ–Њ–ї—М–Ј–Њ–≤–∞–љ–Є–µ —Б–µ—А–≤–Є—Б–∞ ClipSaver.ru
жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П
жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П, by Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki?curid=4... / CC BY SA 3.0 #жЧ•жЬЭдЇМеЫљйЦУжЭ°зіД #дЄНеє≥з≠ЙжЭ°зіД #жШОж≤їжЩВдї£гБЃе§ЦдЇ§ #1876еєігБЃжЭ°зіД #йАЪеХЖиИ™жµЈжЭ°зіД #1876еєігБЃжЧ•жЬђ #1876еєігБЃжЬЭйЃЃ жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶П жЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶ПпЉИгБЂгБ£гБ°гВЗгБЖгБЧгВЕгБЖгБУгБЖгБШгВЗгБЖгБНпЉЙгБѓгАБ1876еєіпЉИжШОж≤ї9еєігАБжЩВжЖ≤жЪ¶еЕЙзЈТ2еєіпЉЭйЂШеЃЧ13еєіпЉЙ2жЬИ26жЧ•гБЂжЧ•жЬђгБ®жЭОж∞ПжЬЭйЃЃгБ®гБЃйЦУгБІзЈ†зµРгБХгВМгБЯжЭ°зіДгБ®гБЭгВМгБЂдїШйЪПгБЧгБЯиЂЄеНФеЃЪгВТеРЂгВБгБ¶жМЗгБЩгАВжЭ°зіДж≠£жЦЗгБІгБѓгАМдњЃе•љжЭ°и¶ПгАНгБ®гБЃгБњи®ШгБХгВМгБ¶гБДгВЛгБМгАБйАЪдЊЛгБ®гБЧгБ¶жЬЭйЃЃеЬЛгБ®гБЃдњЃе•љжЭ°и¶ПпЉИгБ°гВЗгБЖгБЫгВУгБУгБПгБ®гБЃ-пЉЙгАБжЧ•жЬЭдњЃе•љжЭ°и¶ПгАБжЧ•йЃЃдњЃе•љжЭ°и¶ПпЉИгБЂгБ£гБЫгВУ-пЉЙгБ™гБ©гБ®еСЉзІ∞гБЩгВЛгАВељУжЩВжЭ±гВҐгВЄгВҐгБІзµРгБ∞гВМгБЯе§ЪгБПгБЃжЭ°зіДгБ®еРМжІШгАБдЄНеє≥з≠ЙжЭ°зіДгБІгБВгБ£гБЯгАВ ж±ЯиПѓе≥ґгБІи™њеН∞гБХгВМгБЯгБЯгВБж±ЯиПѓе≥ґжЭ°зіДпЉИгВЂгГ≥гГХгВ°гГЙ/гБУгБЖгБЛгБ®гБЖ гБШгВЗгБЖгВДгБПгАБжЬЭпЉЪпЉЙгБ®гВВгАБдЄЩе≠РгБЃеєігБЂзµРгБ∞гВМгБЯгБЯгВБгБЂдЄЩе≠РдњЃдЇ§жЭ°зіДпЉИгБЄгБДгБЧгБЧгВЕгБЖгБУгБЖгБШгВЗгБЖгВДгБПгАБжЬЭпЉЪпЉЙгБ®гВВгБДгБЖгАВ 1875еєігБЂиµЈгБНгБЯж±ЯиПѓе≥ґдЇЛдїґгБЃеЊМгАБжЧ•жЬЭйЦУгБІзµРгБ∞гВМгБЯжЭ°зіДгБІгБВгВЛгБМгАБжЭ°зіДгБЭгБЃгВВгБЃгБѓеЕ®12жђЊгБЛгВЙжИРгВКгАБгБЭгВМгБ®гБѓеИ•гБЂеЕЈдљУзЪДгБ™гБУгБ®гВТеЃЪгВБгБЯдїШе±ЮжЦЗжЫЄгБМеЕ®11жђЊгАБи≤њжШУи¶ПеЙЗ11еЙЗгАБеПКгБ≥еЕђжЦЗгБМгБВгВЛгАВгБУгВМгВЙеЕ®гБ¶гВТеРЂгВУгБІдЄАдљУгБЃгВВгБЃгБ®гБХгВМгВЛгАВ гАМжЬЭйЃЃгБМжЄЕжЬЭгБЃеЖКе∞БгБЛгВЙзЛђзЂЛгБЧгБЯеЫљеЃґдЄїж®©гВТжЬЙгБЩгВЛзЛђзЂЛеЫљгБІгБВгВЛгБУгБ®гАНгВТжШОи®ШгБЧгБЯгБМгАБгАМзЙЗеЛЩзЪДй†ШдЇЛи£БеИ§ж®©гБЃи®≠еЃЪгАНгВДгАМйЦҐз®ОиЗ™дЄїж®©гБЃе֙姱гАНгБ®гБДгБ£гБЯдЄНеє≥з≠ЙжЭ°зіДзЪДжЭ°й†ЕгВТеЖЕеЃєгБ®гБЩгВЛгБУгБ®гБ™гБ©гБМгАБгБЭгБЃзЙєеЊігБІгБВгВЛгАВ жЬЭйЃЃеБігБЂгБѓдЄНеИ©гБ™еЖЕеЃєгБ®гБ™гБ£гБ¶гБДгВЛгБМгАБгБЭгВМгБЊгБІдЄЦзХМгБ®гБѓйЩРеЃЪзЪДгБ™еЫљдЇ§гБЧгБЛжМБгБЯгБ™гБЛгБ£гБЯжЬЭйЃЃгБМйЦЛеЫљгБЩгВЛе•Сж©ЯгБ®гБ™гБ£гБЯжЭ°зіДгБІгБВгВЛгАВгБЭгБЃеЊМжЬЭйЃЃгБѓдЉЉгБЯгВИгБЖгБ™еЖЕеЃєгБЃжЭ°зіДгВТдїЦгБЃи•њжіЛиЂЄеЫљпЉИгВҐгГ°гГ™гВЂеРИи°ЖеЫљгАБгВ§гВЃгГ™гВєгАБеЄЭжФњгГЙгВ§гГДгАБеЄЭжФњгГ≠гВЈгВҐгАБгГХгГ©гГ≥гВєпЉЙгБ®гВВеРМжІШгБЃжЭ°зіДгВТзЈ†зµРгБЩгВЛгБУгБ®гБ®гБ™гБ£гБЯгАВ гБУгБЃжЭ°зіДгБМзЈ†зµРгБХгВМгБЯељУжЩВгАБжЬЭйЃЃгБѓжЄЕгБЃеЖКе∞БеЫљгБІгБВгБ£гБЯгБМгАБйОЦеЫљжФњз≠ЦгВТеЫљжШѓгБ®гБЧгБ¶гБДгБЯгБЯгВБгАБеЫљйЪЫдЇ§жµБгБѓйЭЮеЄЄгБЂйЩРгВЙгВМгБ¶гБДгБЯгАВгБЧгБЛгБЧгАБгБЭгБЃгВИгБЖгБ™жЬЭйЃЃгВВ1860еєідї£дї•йЩНгБЂжђІз±≥еИЧеЉЈгБЛгВЙињСдї£зЪДгБ™еЫљдЇ§пљ•йАЪеХЖйЦҐдњВгВТж±ВгВБгВЙгВМгВЛгВИгБЖгБЂгБ™гВЛгАВ ељУжЩВгАБжЬЭйЃЃгБЃжФњж®©гВТжЛЕгБ£гБ¶гБДгБЯгБЃгБѓйЂШеЃЧгБЃеЃЯзИґиИИеЃ£е§ІйЩҐеРЫгБІгБВгВЛгАВе§ІйЩҐеРЫгБѓйОЦеЫљгВТзґ≠жМБгБЩгВЛеІњеЛҐгВТи≤ЂгБДгБЯгАВгБУгВМгБѓдЄ≠еЫљгБЂгБКгБСгВЛи•њжђІеБігБЃи°МзВЇгВТзЯ•гБ£гБЯгБУгБ®гВВгБВгВЛгБМгАБжЬ±е≠Ре≠¶дї•е§ЦгВТи™НгВБгБ™гБДи°Ыж≠£жЦ•йВ™гБ®гБДгБЖжАЭжГ≥жФњз≠ЦгВТжО®йА≤гБЧгБ¶гБДгБЯе§ІйЩҐеРЫгБМи•њжђІиЂЄеЫљгВТе§ЈзЛДи¶ЦгБЧгБ¶гБДгБЯгБУгБ®гВВзРЖзФ±гБЃдЄАгБ§гБІгБВгВЛгАВе§ІйЩҐеРЫгБѓгАМи•њжіЛиЫЃдЇЇгБЃдЊµзКѓгБЂжИ¶гВПгБ™гБДдЇЛгБѓеТМи≠∞гВТгБЩгВЛдЇЛгБІгБВгВКгАБеТМи≠∞гВТдЄїеЉµгБЩгВЛгБУгБ®гБѓе£≤еЫљи°МзВЇгБІгБВгВЛгАНгБ®жЫЄгБЛгВМгБЯжЦ•еТМзҐСгВТжЬЭйЃЃеРДеЬ∞гБЂеїЇгБ¶гАБжФШе§ЈгБЃж©ЯйБЛгВТйЂШгВБгБЯгАВгБЊгБЯгАБжЬЭйЃЃгБІгБѓгАБжЦЗз¶ДгГїжЕґйХЈгБЃељєгБІдЄ≠еЫљгБМжЬЭйЃЃгВТжХСжПігБЧгБЯгБЯгВБгАБжИ¶жЩВгБЂгБѓдЄ≠еЫљгБЛгВЙгБЃжХСжПігВТжЬЯеЊЕгБЧгБ¶гБДгБЯгАВе∞Пе≥ґжѓЕгБѓгАМдЄ≠еЫљгБѓжЭ±гВҐгВЄгВҐеЕ®дљУгБЂгБ®гБ£гБ¶гБЃи¶™еИЖгБ†гБ®гБДгБЖгБЃгБМжЬЭйЃЃгБЃи™Ни≠ШгБІгБЩгБЛгВЙгАБ趙еИЖгБІгБВгВЛдЄ≠еЫљгБЂиЗ™еИЖгВТеЃИгБ£гБ¶гВВгВЙгБКгБЖгБ®гБЩгВЛгВПгБСгБІгБЩгБ≠гАНгБ®ињ∞гБєгБ¶гБДгВЛгАВ гБЧгБЛгБЧгБ™гБМгВЙгАБ1866еєігБЃгГХгГ©гГ≥гВєдЇЇеЃ£жХЩеЄЂгВТеРЂгВАгВ≠гГ™гВєгГИжХЩеЊТгБЃиЩРжЃЇдЇЛдїґпЉИдЄЩеѓЕињЂеЃ≥пЉЙгБѓе†±еЊ©гБ®гБЧгБ¶гГХгГ©гГ≥гВєиїНгБМиїНиЙ¶7йЪїзЈПеЕµеКЫ1000дЇЇгБІжЬЭйЃЃгБЃж±ЯиПѓе≥ґгВТжФїжТГгГїеН†й†ШгБЩгВЛдЄЩеѓЕжіЛжУЊгБ®гБ™гВКгАБеРМеєігБЃгВЄгВІгГНгГ©гГЂгГїгВЈгГ£гГЉгГЮгГ≥еПЈгВТзДЉгБНи®ОгБ°дЇЛдїґгБѓгВҐгГ°гГ™гВЂеРИи°ЖеЫљгВВ冱匩гБ®гБЧгБ¶иїНиЙ¶5йЪїзЈПеЕµеКЫ1200дЇЇиЙ¶з†≤85йЦАгБІжЬЭйЃЃгБЃж±ЯиПѓе≥ґгБЂжФїжТГгГїеН†й†ШгВТи°МгВПгВМгВЛпЉИиЊЫжЬ™жіЛжУЊпЉЙгБ®гБДгБЖдЇЛжЕЛгВТжЛЫгБДгБЯгАВ и•њжђІеИЧеЉЈгБМињЂгБ£гБ¶гБДгБЯжЭ±гВҐгВЄгВҐиЂЄеЫљгБЃдЄ≠гБІгАБгБДгБ°гБѓгВДгБПйЦЛеЫљгБЧжШОж≤їзґ≠жЦ∞гБЂгВИгВКињСдї£еЫљеЃґгБ®гБ™гБ£гБЯжЧ•жЬђгБѓгАБи•њжђІиЂЄеЫљгБЃгБњгБ™гВЙгБЪгАБиЗ™еЫљеС®иЊЇгБЃгВҐгВЄгВҐиЂЄеЫљгБ®гВВињСдї£зЪДгБ™еЫљйЪЫйЦҐдњВгВТж®єзЂЛгБЧгВИгБЖгБ®гБЧгБЯгАВжЬЭйЃЃгБЂгВВ1868еєі12жЬИгБЂжШОж≤їжФњеЇЬгБМж®єзЂЛгБЩгВЛгБ®гБЩгБРгБЂжЫЄе•СгАБгБЩгБ™гВПгБ°еЫљжЫЄгВТеѓЊй¶ђиЧ©гБЃеЃЧж∞ПгВТдїЛгБЧйАБгБ£гБЯгАВж±ЯжИЄжЩВдї£гВТйАЪгБШгБ¶гАБжЬЭйЃЃгБ®гБЃйЦҐдњВгБѓеЃЧж∞ПгВТйАЪгБШзѓЙгБЛгВМгБ¶гБДгБЯгБЯгВБгБІгБВгВЛгАВгБЧгБЛгБЧеЫљжЫЄгБЃдЄ≠гБЂгАМзЪЗгАНгВДгАМе•ЙеЛЕгАНгБ®гБДгБ£гБЯзФ®и™ЮгБМдљњзФ®гБХгВМгБ¶гБДгБЯгБЯгВБгБЂгАБжЬЭйЃЃеБігБѓеПЧгБСеПЦгВКгВТжЛТеР¶гБЧгБЯгАВеЙНињСдї£гБЂгБКгБСгВЛеЖКе∞БдљУеИґдЄЛгБЂгБКгБДгБ¶гАБгАМзЪЗдЄКгАНгВДгАМе•ЙеЛЕгАНгБ®гБДгБЖзФ®и™ЮгБѓдЄ≠еЫљгБЃзОЛжЬЭгБЂгБЃгБњи®±гБХгВМгБЯзФ®и™ЮгБІгБВгБ£гБ¶гАБжЧ•жЬђгБМгБЭгВМгВТдљњзФ®гБЩгВЛгБ®гБДгБЖгБУгБ®гБѓгАБеЖКе∞БдљУеИґгБЃй†ВзВєгБЂзЂЛгБ°жЬЭйЃЃгВИгВКгВВжЧ•жЬђгБЃеЫљйЪЫеЬ∞дљНгВТдЄКгБ®гБЩгВЛгБУгБ®гВТзФїз≠ЦгБЧгБЯгБ®жЬЭйЃЃгБѓжНЙгБИгБЯгБЃгБІгБВгВЛгАВ жЧІжЪ¶гБІжШОж≤їеЕГеєігБЂгБВгБЯгВЛ1868еєідї•жЭ•гАБдљХеЇ¶гБЛжЬЭйЃЃеЃЫгБ¶гБЃжЧ•жЬђгБЛгВЙгБЃеЫљжЫЄгБМгВВгБЯгВЙгБХгВМгБЯгБМгАБдЄ°еЫљгБЃйЦҐдњВгБѓеЖЖжїСгБ™гВВгБЃгБ®гБѓи®АгБИгБ™гБЛгБ£гБЯгАВжЫЄе•СеХПй°МгВТиГМжЩѓгБ®гБЧгБ¶зФЯгБШгБЯжЧ•жЬђеЫљеЖЕгБЂгБКгБСгВЛгАМеЊБйЯУиЂЦгАНгБЃйЂШгБЊгВКгБЂгАБе§ІйЩҐеРЫгБМйЭЮеЄЄгБ™и≠¶жИТењГгВТжК±гБДгБЯгБУгБ®гВВдЄАеЫ†гБІгБВгВЛгАВгБЊгБЯгАБйХЈеіОгБЃеЗЇе≥ґгБЃгВИгБЖгБЂйЗЬе±±гБЃеА≠駮гБЂйЩРеЃЪгБЧгБЯеЫљдЇ§гВТжЬЫгВАжЬЭйЃЃеБігБ®гАБеѓЊй¶ђеЃЧж∞ПгБЛгВЙе§ЦдЇ§ж®©гВТеПЦгВКдЄКгБТгБ¶е§ЦдЇ§гВТдЄАеЕГеМЦгБЧгАБйЦЛеЫљгВТињЂгВЛжЧ•жЬђгБ®гБЃйЦУгБЂйљЯйљђгБМзФЯгБШгБЯгАВйЗЬе±±гБЃеА≠駮гБѓжЬЭйЃЃеБігБМжЧ•жЬђгАБзЙєгБЂеѓЊй¶ђиЧ©гБЃдљњзѓАгВДеХЖдЇЇгВТй•ЧењЬгБЩгВЛгБЯгВБгБЂи®≠гБСгБЯжЦљи®≠гБІгБВгБ£гБЯгБМгАБжШОж≤їжФњеЇЬгБѓеѓЊй¶ђиЧ©гБЛгВЙе§ЦдЇ§ж®©гВТеПЦгВКдЄКгБТгАБжЬЭйЃЃгБ®гБЃдЇ§жЄЙгБЂдєЧгВКеЗЇгБЭгБЖгБ®гБЧгБЯгАВгБЭгБЃйЪЫгАБеА≠駮гВТгВВжЬЭйЃЃеБі...