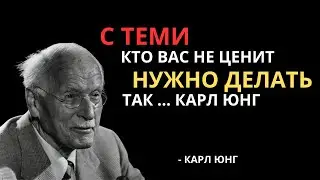知的障害者福祉法 7割を目指す講義NO.13 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 скачать в хорошем качестве
Повторяем попытку...

Скачать видео с ютуб по ссылке или смотреть без блокировок на сайте: 知的障害者福祉法 7割を目指す講義NO.13 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 в качестве 4k
У нас вы можете посмотреть бесплатно 知的障害者福祉法 7割を目指す講義NO.13 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 или скачать в максимальном доступном качестве, видео которое было загружено на ютуб. Для загрузки выберите вариант из формы ниже:
-
Информация по загрузке:
Скачать mp3 с ютуба отдельным файлом. Бесплатный рингтон 知的障害者福祉法 7割を目指す講義NO.13 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 в формате MP3:
Если кнопки скачивания не
загрузились
НАЖМИТЕ ЗДЕСЬ или обновите страницу
Если возникают проблемы со скачиванием видео, пожалуйста напишите в поддержку по адресу внизу
страницы.
Спасибо за использование сервиса ClipSaver.ru
知的障害者福祉法 7割を目指す講義NO.13 障害者に対する支援と障害者自立支援制度
愛知県の知多半島内半田市にあるアール総合法律事務所の弁護士・社会福祉士の榊原尚之と申します。 講師歴としては、元東京アカデミー講師、日本福祉大学ゲスト講師、元名城大学大学院非常勤講師 今後も福祉系の動画を配信していきますので、チャンネル登録をお願いします。 / @swsakaki ツイッターは、こちら 国家試験に有益な情報をつぶやいています。 / h5nlyjozrqzjy81 インスタは、こちら 国家試験に有益な情報を表等にしてアップしています。 / swsakaki お薦めの書籍等 楽天アフィリエイトリンクとアマゾンアフィリエイトリンクです。 社会学がわかる事典 社会学に興味が湧く名著です。 楽天はこちら https://a.r10.to/hMLN8T アマゾンはこちら https://amzn.to/3QI9Nc9 勉強して疲れた時はこれがお薦めです! ヘルプマン! 高齢分野のコミック 楽天はこちら https://a.r10.to/h5XR1v アマゾンはこちら https://amzn.to/3FztVKQ 吉岡里帆主演のドラマ「健康で文化的な最低限度の生活」 楽天はこちら https://a.r10.to/h5bIaX アマゾンはこちら https://amzn.to/3StMN1O 深田恭子主演のドラマ「サイレント・プア」 楽天はこちら https://a.r10.to/hMTx7B アマゾンはこちら https://amzn.to/3P2MuZx 7割を目指す講義NO.13 知的障害者福祉法の一部 1.知的障害者福祉法の成立の背景と経緯 知的障害者に対する福祉法である精神薄弱者福祉法は、敗戦から15年後の1960年、昭和35年に成立しました。 敗戦が、1945年ですから、敗戦から15年後のことで、知的障害者の福祉は後回しにされてきました。 精神薄弱者福祉法が制定されるまでは、成人の精神薄弱者の入所施設はありませんでした。要するに、精神薄弱児には児童福祉法で精神薄弱児施設があるのに対し、成人の精神薄弱者には入所施設がありませんでした。 では、精神薄弱児が18歳になったら、どうなるのか。 この点、特例措置として、年齢超過児を児童福祉法に定められた精神薄弱児施設において、その居場所を確保していました。当然ですが、精神薄弱児施設での年齢超過児がどんどんと増加していくわけです。特例措置もいよいよ限界に達してきて、児童と成人との施策のアンバランスさが目立ち始めたわけです。 この時に、精神薄弱児(知的障害児)を持つ家族の親の会が、「このままでは自分たちの子どもの行き場所がない!」と声を上げたということもありました。 そこで、成人になった精神薄弱者(知的障害者)の居場所を確保するため、精神薄弱者福祉法を制定し、精神薄弱者援護施設を法的に位置付け、入所施設の設置体制を整備したわけです。 この時期は、日本においては、高度経済成長期であったので、国にもお金に余力がありました。そこで、日本では、行く場所がないという知的障害者に対し、施設をどんどん建てて、その施設に入所させたわけです。 ちなみに身体障害者に対する福祉法である身体障害者福祉法は、敗戦から4年後の1949年に成立しています。 このような経緯で成立した精神薄弱者福祉法は、18歳以上の知的障害者に対する福祉施策の根拠となるものです(18歳未満の知的障害者に対しては児童福祉法の対象となります)。 その後、1971年12月には、国連総会にて、動きがありました。 知的障害者の権利宣言の採択がありました。 また、その4年後の1975年には、国連総会において、障害者の権利宣言が採択されました。 まずは、知的障害者の権利宣言があって、その後に障害者一般の権利宣言が採択されたという順番も押さえておいてください。 このような障害者の自立生活を重視する動きがあったこと、権利擁護に対する国際的や国内的な機運が高まるなどしていました。 そして、1990年には、福祉関係八法改正があり、知的障害者の援護の実施主体が、都道府県から市町村に移されました(第9条、第15条の4、第16条)。すなわち、市町村が、18歳以上の知的障害者につき、障害支援施設への入所措置権限を有するようになったわけです。 そして、1998年、平成10年には、法律の名称も、精神薄弱者福祉法から「知的障害者福祉法」に名称変更されました。 2.知的障害者福祉法の目的について 福祉の分野の大きな流れとして、1998年ころからの社会福祉基礎構造改革(措置制度から契約制度へ)という流れがあります。その中で、2000年、平成12年の知的障害者福祉法改正では、法の目的として、従来からの生活支援だけではなく、知的障害者の自立と社会経済生活への参加の促進があげられて、知的障害者も生活の主体者としての地位が法的に確認されました。 これは、何を意味するのかというと、それまでは知的障害者は支援の対象でしかなく、一人の人間として認めてこなかったということです。 3.定義 知的障害者は、身体障害者や精神障害者とは異なり、法的な裏付けは存在しません。 これは、どうしてか。 知的障害というものは、発達であったり、成長であったりといった要素が絡んでくるので、定義が難しいことによります。 なので、法律ではなく、厚生事務次官による「療育手帳制度について」という通知によって知的障害者の定義が規定されています。 「知的機能の障害が発達期(おおむね18歳まで)にあらわれ、日常生活に支障が生じているため、何らかの特別の援助を必要とする状態にあるもの」とあります。 ですから、大人になってから事故などで知的機能に障害が出た場合は、「知的障害」には含まれません。おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、それが持続している場合には、18歳以上の方でも療育手帳を取得できる余地があります。 4.判定 障害程度の判定場所は、18歳未満の場合と18歳以上の場合とで異なっています。 18歳未満の場合は各都道府県の児童相談所 18歳以上は知的障害者更生相談所 の判定に基づきます。 申請先ですが、福祉事務所(ない場合は町村)になります。 ②知的障害者更生相談所 都道府県では、知的障害者更生相談所を設置しなければならないことになっています(第12条第1項)。 知的障害者更生相談所の業務としては、市町村相互間の連絡調整、市町村への情報提供、その他必要な援助、18歳以上の知的障害者の医学的、心理学的及び職能的判定等があります(第12条第2項)。 ちなみに、指定都市では、知的障害者更生相談所を設置することができる、つまり、任意設置になっています。 知的障害者に関連する業務の実施主体については、基本的には、市町村の福祉事務所で行い、都道府県は、市町村に対するパックアップをすることになっています。 ③知的障害者福祉司 市町村の設置する福祉事務所では、知的障害者福祉司が任意設置になっています(第13条第2項)。都道府県の知的障害者更生相談所では、必置(第13条第1項)になっています。 都道府県の知的障害者福祉司は、市町村の更生援護の実施に関する業務や、知的障害者に関する相談及び指導のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものを行います(第13条第3項)。 市町村の知的障害者福祉司は、福祉事務所の所員に対し、技術的指導を行い、知的障害者の相談等に応じ、専門的な知識及び技術を必要とするものを行います(第13条第4項)。 知的障害者福祉司の任用資格として、社会福祉主事たる資格を有する者であって、知的障害者の福祉に関する事業に2年以上従事した経験を有するもの、社会福祉士などが規定されています(第14条第1号、第4号)。 5.実施体制について ①市町村 市町村の福祉事務所が知的障害者の福祉に関し、業務を行います(第10条)。 知的障害者の福祉に関して、実情の把握、情報の提供、応相談、調査、指導等を行います(第9条第5項)。 それから、市町村は、18歳以上の知的障害者につき、やむを得ない事由により介護給付費等(療養介護等に係るものに限る)の支給を受けることが著しく困難であると認めるときは、その福祉を図るため、必要に応じ、障害者支援施設等への入所措置を取らなければならないことになっています(第16条第1項第2号)。 #社会福祉士 #障害者に対する支援と障害者自立支援制度 #知的障害者福祉法 #障害者総合支援法 #療育手帳